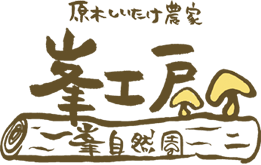近代以降の有名作家の中には食への探求心や執着が強く、作品の中にそれを記した方が多くいます。
有名な作家が好んだ「ご飯のお供」をみてみましょう。
座禅豆

芸妓(げいぎ)や女給など女性の境遇の表現が逸品の永井荷風(1879〜1959)は、気に入った店ばかりに出かけたましたが、日記『断腸亭日乗』に、ひとり暮らしならではのつつましき贅沢を楽しみ、『新橋玉木屋の座禅豆』を好んだと記しています。
川魚の佃煮

美食の先駆者、北大路魯山人(1883〜1959)は随筆『日常美食の秘訣』で、「飯は最後のとどめを刺すもの」と、いかに米と炊き方が大切かを説いています。とくにお茶漬けを愛し、納豆茶漬け、天ぷら茶漬け、鱧(はも)の茶漬けのほか、「天下一品の贅沢。茶漬けの王者」と評したのが『ゴリの茶漬け』です。
ゴリはハゼなど小さな川魚のことで、魯山人は京都の桂川で獲れたゴリを生醬油で佃煮にし、熱々のご飯にのせて茶をかけて食べていたそうです。
漬物

家の宇野千代(1897〜1996)は、自炊の食道楽を楽しみ、到来物(いただき物)を気に入ると、そればかり……。鱸(すずき)の塩焼き、松葉蟹、ラーメンなどを取り寄せたそうです。レシピ本も著したほどですが、郷里、山口県岩国の漬物店『うまもんの漬物』を欠かさなかったそうです。
すじこ納豆

太宰治(1909〜48)は、自他ともに認める大食漢で、故郷、青森の味をこよなく愛しました。
太宰の妻、津島美知子の『回想の太宰』には、若生昆布(1年ものの若い昆布)で包んだおむすび、ミズ(ウワバミソウ)とホヤの水煮など、青森の郷土料理を好んだという記載があります。なかでも納豆に筋子を混ぜた『筋子納豆』を白飯や豆腐にのせて食べていたそうです。
金山寺味噌

英文学者で作家の吉田健一(1912〜77)は、贅沢な酒肴を追求しましたが、「飯は一菜だけで楽しんで食べられる」とし、味噌を仕込む時に白うりなどを漬け熟成させた、なめみそ『金山寺味噌』を絶賛。が、そこに、佃煮や紫蘇の実、胡麻塩、茄子の辛子漬け、白子干しなどがあれば「法悦の境になる」と『舌鼓ところどころ私の食物史』に記しています。
【峯工房おすすめのご飯のおとも】
 ご飯のお供に贅沢セットB 【おかず4種レギュラーセット(原木椎茸・原木椎茸使用:湧水使用出汁・しいたけと玉ねぎのなんでもソース・椎茸と季節野菜ピクルス)】2,850円(税込)
ご飯のお供に贅沢セットB 【おかず4種レギュラーセット(原木椎茸・原木椎茸使用:湧水使用出汁・しいたけと玉ねぎのなんでもソース・椎茸と季節野菜ピクルス)】2,850円(税込) よくばりセット 【しいたけとたまねぎのなんでもソース≪レギュラーサイズ≫220ml×3本】2,400円(税込)
よくばりセット 【しいたけとたまねぎのなんでもソース≪レギュラーサイズ≫220ml×3本】2,400円(税込) よくばりセット 【しいたけ味噌≪お得サイズ≫ 260g×3本】4,050円(税込)
よくばりセット 【しいたけ味噌≪お得サイズ≫ 260g×3本】4,050円(税込) ご飯のお供に【おかず3種レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】2,610円(税込)
ご飯のお供に【おかず3種レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】2,610円(税込) ご飯のお供に【おかず3種6個レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】5,220円(税込)
ご飯のお供に【おかず3種6個レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】5,220円(税込) 峯セット【ふき】3,050円(税込)
峯セット【ふき】3,050円(税込)