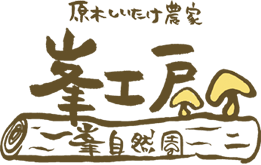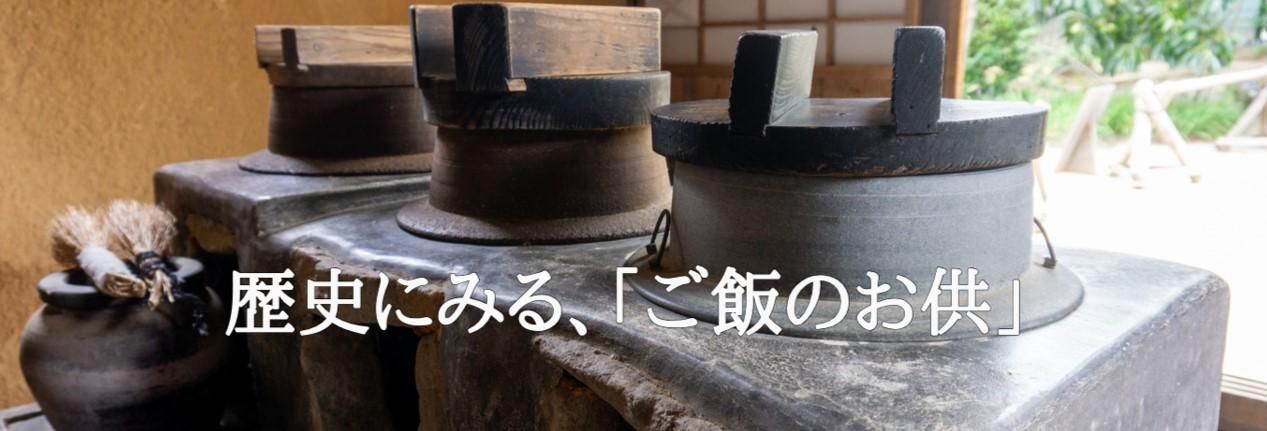
歴史にみる、「ご飯のお供」
日本人とご飯、そして「ご飯のお供」は切り離せない間柄です。
「ご飯のお供」の歴史は古く、稲作が広まった弥生時代までさかのぼります。
稲作が伝来したのは約6000年前の縄文時代で、その後、弥生時代に急速に広まり、ご飯と副菜の組み合わせが確立していきます。飛鳥・奈良時代になるとご飯、汁物、漬物という一汁一菜が一般的になっていき、平安時代の貴族は毎食、複数のおかずが揃えられるようになったそうです。
昔の人々はどんな「ご飯のお供」を食べていたのでしょうか。
梅干し

梅干しの原型といえる『梅の塩漬け』が書物に登場するのは平安中期ですが、梅干しとして広まったのは、鎌倉幕府を創立した源頼朝の正室として知られる北条政子のおかげです。
政子は、『梅干しおむすび』を兵たちに与えて、承久の乱(1221)で勝利を得たとか。梅干しの抗菌作用が食中毒や傷の消毒に役立ち、以降、梅の栽培が広まったそうです。
焼き味噌

織田信長(1534〜82)は、焼き味噌をのせた冷や飯に湯をかけた『焼き味噌湯漬け』を好んだそうです。「尾張の豆味噌を直火で炙り、すり下ろした生姜や胡麻を混ぜて食べていたそうです。テレビドラマなどでも、信長が立ったまま湯漬けを掻っ込むシーンが描かれることがありますね。
鰹節

戦国時代は携帯しやすく、刃物で削れば食べられる手軽さから、『鰹節』が兵糧として重宝したそうです。
徳川家3代に仕えた大久保彦左衛門(1560〜1639)も、『三河物語』に、「かじれば力になる」と記しています。鰹節は“勝男武士”と書くこともできるため、縁起担ぎにも一役買ったのでは。ご飯に削った鰹節をのせて食べていたことが想像できます。
自然薯とろろ

戦国の世を勝ち取った徳川家康(1542〜1616)は、健康と食に気を使い、長生きしました。徳川家康の好物、自然薯をすり下ろしたとろろをご飯にのせた『とろろ飯』は、今も静岡の名物です。
【峯工房おすすめのご飯のおとも】
 ご飯のお供に贅沢セットB 【おかず4種レギュラーセット(原木椎茸・原木椎茸使用:湧水使用出汁・しいたけと玉ねぎのなんでもソース・椎茸と季節野菜ピクルス)】2,850円(税込)
ご飯のお供に贅沢セットB 【おかず4種レギュラーセット(原木椎茸・原木椎茸使用:湧水使用出汁・しいたけと玉ねぎのなんでもソース・椎茸と季節野菜ピクルス)】2,850円(税込) よくばりセット 【しいたけとたまねぎのなんでもソース≪レギュラーサイズ≫220ml×3本】2,400円(税込)
よくばりセット 【しいたけとたまねぎのなんでもソース≪レギュラーサイズ≫220ml×3本】2,400円(税込) よくばりセット 【しいたけ味噌≪お得サイズ≫ 260g×3本】4,050円(税込)
よくばりセット 【しいたけ味噌≪お得サイズ≫ 260g×3本】4,050円(税込) ご飯のお供に【おかず3種レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】2,610円(税込)
ご飯のお供に【おかず3種レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】2,610円(税込) ご飯のお供に【おかず3種6個レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】5,220円(税込)
ご飯のお供に【おかず3種6個レギュラーセット(原木椎茸・原木使用:しいたけ味噌・しいたけと玉ねぎのなんでもソース)】5,220円(税込) 峯セット【ふき】3,050円(税込)
峯セット【ふき】3,050円(税込)